本当に「アメリカは内戦に向かう」のか=インドはモディ体制で民主主義後退?
長田浩一 2024年7月31日(水) 7時30分
拡大
11月に行われる米国大統領選挙は民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領の対決の構図が確実になった。写真はワシントン。
(1 / 2 枚)
11月に行われる米国大統領選挙は民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領の対決の構図が確実になった。米大統領選といえば思い出すのが、前回の選挙で敗れたトランプ支持派による国会議事堂襲撃事件。選挙結果を覆そうとするクーデター未遂とも言え、米国の民主主義を揺るがす大事件として世界に衝撃を与えた。その後も社会の分断が進み、内戦をテーマにした映画まで公開される状況下、再び同様の事態が発生する恐れはないのだろうか。
【その他の写真】
映画「シビル・ウォー」日本でも公開へ
問題の映画はアレックス・ガーランド監督の「Civil War」。直訳するとそのものずばり「内戦」だ。今年4月に米国で公開され、2週連続で興行収入ナンバーワンを記録したという。日本では「シビル・ウォー アメリカ最後の日」の邦題で10月に公開される予定だ。
映画情報サイトなどによると、近未来の米国で、権威主義的な大統領が率いる連邦政府から19もの州が離脱。そしてカリフォルニアとテキサスが同盟した「西部勢力」と連邦政府の対立が武力衝突に発展し、内戦が勃発した。そうした中、4人のジャーナリストが大統領にインタビューするためニューヨークからワシントンに向かうが、彼らも戦闘に巻き込まれ、多くの残虐行為を目にする…といったストーリーのようだ。
もちろんこれはフィクションである。しかし、すでに閲覧可能な同作品の日本語版公式サイトが「あなたが目撃するのはフィクションか。それとも明日の現実なのか」とうたっているように、ある程度の現実味がなければこうした映画は制作されないだろうし、多くの観客を集めることもないだろう。まだ映画を見ていないので確たることは言えないが、社会の分断が進み、実際に議事堂襲撃事件が発生した米国社会の現実を反映した作品と言えるのではないか。
米国は「アノクラシー」に転落
内戦といえば、最近改めて注目されている本がある。2年前に米国で出版され、昨年日本語版が出た「アメリカは内戦に向かうのか」だ。著者はカリフォルニア大学サンディエゴ校政治学教授のバーバラ・F・ウォルター氏。あまりにも直截的なタイトルに驚くが、原題(「How Civil Wars Start」=内戦はいかに始まるか)より、日本語版のタイトルの方が内容をより分かりやすく表しているように思う。
同書によると、民主主義が良く機能している社会では内戦が起きる可能性は低い。逆に締め付けの厳しい専制国家でも同様だ。一方で、その中間に位置する「アノクラシー」と呼ばれる国家では、内戦のリスクは跳ね上がる。そして、トランプ大統領(当時)の一連の強権的な行為―議会を軽視した行政命令による統治、新型コロナ対策を強化しようとする州知事への恫喝、郵便投票無力化の試みなど―に加え、2021年1月6日の国会議事堂襲撃事件により、米国は民主主義国家からアノクラシー国家に転落したと説く。保守派判事が多数を占める連邦最高裁判所が今年7月初め、トランプ氏を念頭に大統領経験者の刑事責任は部分的に免責されるとの判断を下した現在(リベラル派の判事は「いまや大統領は法の上に立つ王になった」と批判)、民主主義はさらに打撃を受けたと言えるのかもしれない。
では、11月の大統領選挙の結果次第で、内戦または何らかのトラブルは起きるのか。ウォルター教授は「月刊文芸春秋」8月号のインタビューで「彼(トランプ氏)が勝ったら短期的には暴力事件は起きなくなると思います。彼が負けたら、いくつかの暴力事件が発生するかもしれません」と予測。アメリカ政治が専門の久保文明防衛大学校長は、7月に放送されたテレビ番組で「もしトランプ氏が選挙に負けた場合、負けを認めるかは興味深い問題だ」と語った。専門家の多くは、映画のような全面的な内戦は考えにくいとしても、トランプ氏が選挙で敗れた場合にはただでは済まない可能性があると考えているようだ。民主主義国のリーダーであるべき米国で、再びその土台を揺るがすような事態が起きるのか。注視していきたい。
「世界最大の民主主義国」が権威主義に?
その米国が中心となっている「日米豪印戦略対話(クアッド)」は、海洋進出を続ける中国への対抗軸として、米国、日本、オーストラリア、インドの4カ国で構成される枠組みだ。「自由で開かれたインド太平洋」をうたい文句として、この地域で民主主義の価値観を共有する4大国を糾合した組織として2019年から本格的に始動した。しかし、米国の民主主義に影が差しているのは前述の通り。さらに人口世界一のインドについても、「世界最大の民主主義国」という別称がふさわしいのか、怪しくなっているようだ。

このほど出版された「『モディ化』するインド―大国幻想が生み出した権威主義」(湊一樹著)は、2014年に政権を握ったナレンドラ・モディ首相の下、ヒンズー至上主義によるイスラム教徒への迫害や、自身の神格化や報道への規制などを通じた権威主義の強化により、インドの民主主義が後退していく様子を描いて実に興味深い。湊氏はアジア経済研究所地域研究センター研究員で、インドを中心とする南アジア政治の専門家。その舌鋒は鋭く、「モディ政権の10年でインドは大きく変わった。…『世界最大の民主主義国』と呼ばれてきたインドが、民主主義の後退を経て権威主義化の道を足早に歩んでいる」と指摘したうえで、「モディ政治は非民主的である」と言い切っている。他人事ながら、筆者が次にインドを訪れるとき、無事に入国できるのか心配したくなるほどだ。
こうしたインドの実情は、日本では意外なほど知られていない。それについて湊氏は、中国に対抗するパートナーとしての「民主国家・インド」への期待が膨らんだ結果、「自らの願望を投影した都合のよいインド像が、日本人のあいだに定着」しているとして、インドの内政問題をあまり取り上げないメディアにも批判の矛先を向ける。報道機関OBとして、この指摘には「その通り」と頭を下げるしかない。
このように民主主義の後退が懸念されるインドだが、先に行われた総選挙ではモディ首相率いるインド人民党が予想外に大きく議席を減らし、単独過半数を割り込む結果となった。これはインドの民主主義が今なお機能している事実の表れなのか。「(モディ政権の)従来の強権的かつスピーディーな政策運営は変更を余儀なくされる可能性がある」(銀行系シンクタンク)ともみられており、選挙結果が同国の政治・社会にどんな変化をもたらすのか、見守っていきたい。
■筆者プロフィール:長田浩一
1979年時事通信社入社。チューリヒ、フランクフルト特派員、経済部長などを歴任。現在は文章を寄稿したり、地元自治体の市民大学で講師を務めたりの毎日。趣味はサッカー観戦、60歳で始めたジャズピアノ。中国との縁は深くはないが、初めて足を踏み入れた外国の地は北京空港でした。
関連記事
中国はトランプ大統領就任による潜在的影響見越して経済政策調整に着手か―米ゴールドマン専門家
Record China
2024/7/26
ハリス氏がトランプ氏を世論調査でリード、両氏の違いは?―独メディア
Record China
2024/7/25
トランプ氏が当選したら中国は「最大の敵」になるのか―独メディア
Record China
2024/7/19
トランプ氏、間一髪助かったのは横を向いたため?―中国メディア
Record China
2024/7/15
マスク氏の中国訪問、インドに衝撃―独メディア
Record China
2024/5/1
インド、米国からの提案を拒否「NATOプラスに参加するつもりはない」―中国メディア
Record China
2023/6/12
ピックアップ









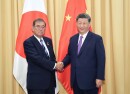



この記事のコメントを見る