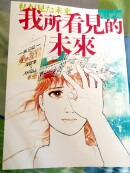中国に伝わる「竜が頭をもたげる日」とは何なのか―民俗学専門家が紹介
拡大
中国では旧暦2月2日が、「竜が頭をもたげる日」と呼ばれてきた。現在の暦では2月下旬から3月上旬ごろだ。つまり、人々が農作業を本格的に始める極めて重要な時期だ。写真は雲南省で撮影。
中国では旧暦2月2日が「竜抬頭」、すなわち「竜が頭をもたげる日」と呼ばれてきた。この日は、その年の豊作を祈る日だった。農作業がそろそろ本格的に始まる時期に豊作を祈ることには納得がいくが、それがどうして竜と関係しているのか。北京師範大学社会学院の人類学民俗学科の蕭放主任教授はこのほど、中国メディアの中国新聞社の取材に応じて、「竜抬頭」の歴史やそれにまつわる習俗や考え方を紹介した。以下は蕭教授の言葉に若干の説明内容を追加するなどで再構成したものだ。
元代には「竜が頭をもたげる日」にまつわる行事が存在した
竜抬頭は中国伝統社会の特性と深い関係がある。中国は農耕社会であり、人々は作物を育て収獲することで、生きながらえてきた。2月の初めにやってくる立春が過ぎれば、人々は農作業を本格的に始める。その時期に豊作を祈り、土地を敬った。
昔の人々は、早春に祭りを行った。社廟に行って祭礼を執り行ってから、皆で酒を飲み太鼓を鳴らすなどした。唐代には、この祭りの日が2月1日に定められ、中和節と呼ばれた。現在の暦で言えば、おおむね2月末から3月の初めに当たる時期だ。そして人々はこの日、野に出て摘んだ野草を食べた。この行事は「富貴を迎えるため」と考えられた。
その後、2月2日が大切な日と考えられるようになった。この日が竜と結びつけられたことを示す最も古い記録は、元代(1279-1368年)に生きた熊夢祥という人物が著した「析津志」だ。元の都は現在の北京の場所に置かれ、「大都」の名で呼ばれた。熊夢祥は大都の風習について、2月2日は「竜抬頭」の日と呼ばれていたと書いている。熊夢祥は、家々ではこの日に、井戸の周辺から家の部屋まで石灰をまいたと説明している。また、この日には掃除をせず、人々は竜の目を恐れたとも書いている。
明代(1368-1644年)に書かれた記録はもっと多い。人々は布を持って屋外から自宅の台所に入り、水瓶を布で巻いた。この風習は「竜を引き戻す」ためと考えられた。竜は神獣であり、雲を立ち上らせ、水をつかさどって雨を降らせる存在と考えられた。人々は竜を敬い、竜を愛した。竜に対する感情は、豊作への祈りが反映されたものだった。
旧暦2月2日と定められたのは、天体観測にも関係している
旧暦2月2日が竜と結びついたのは、古代中国人の天体観測とも関係している。われわれが現在使っている星座は、おおむね古代ギリシャ神話に関係している。しかし恒星の配置に物語を見いだしたのは、中国人も同じだ。中国人は、例えば黄道、すなわち天空における1年をかけての太陽の見かけ上の通り道に、28の星座を設けた。これを「二十八宿」と呼ぶ。二十八宿はさらに「七宿」ごとに4分され、それぞれが、東西南北の方角を守る蒼竜、白虎、朱雀、玄武とされた。蒼竜を構成する七宿はそれぞれ、竜の角や爪、心臓、尾などと考えられた。
2月2日ごろになると、夕刻に竜が東の空に現れるようになる。最初に見えるのは、竜の頭と考えられた星々だ。だから「竜抬頭」と呼ばれるようになった。そしてこの時期は農作業を本格的に始める時期でもある。だから人々は竜に雨ごいの祈りをささげた。
ただし、地平線上に「竜抬頭」の現象が見られる時期は、太陽暦に連動している。それでも人々が月の運行に基づく旧暦の2月2日と結びつけたのは、中国人が月を表す数と日を表す数が合致した日付を特別なものと考えたからだろう。旧暦の1月1日、今でいう春節はもちろん、5月5日、7月7日、9月9日はいずれも、重要な行事の日だった。
強い生命力、竜は民族の精神的活力のシンボルだ
「竜抬頭」の日には、雨乞い以外にも大切なことがあった。「2月2日に竜が頭をもたげると、サソリもムカデも頭を出す」という言い方がある。この日には、虫害を防ぐために、竜に願いをかける日でもあった。食習慣にも特徴があった。食べ物は竜の体の部位と結び付けられた。麺類は竜のひげを意味する「竜須麺」とされた。中国北部でよく食べられる、小麦粉などを水で練って薄く広げて焼く烙餅は竜の鱗だ。また餃子は竜牙(竜の歯)とされた。
「竜抬頭」はこうして、民間信仰として定着したわけだが、現代人にとっては単に雨乞いをしたり虫を追い払うというよりも、新しい1年が始動する高揚した気分と熱い期待を改めて感じる日だ。
中国人にとって竜は、吉祥のシンボルだった。雨や風を司る竜は宮廷文化にも取り入れられて、帝王の象徴にもなった。竜に対する愛着と畏敬の念が根底にある竜文化の生命力は強い。中国語には竜を使った慣用表現が多くある。「竜騰虎躍(竜が舞い上がりトラが跳ねる)」は勢いがよいことの例えだし、「竜馬精神」と言えば、元気旺盛な心意気のことだ。そして中国各地に竜舞が伝わっている。
中国人は海外に移住しても、竜への愛着を失わない。海外でも中国系住民が竜舞を披露することがあり、中国系以外の住人にも人気がある。竜は、民族の精神的活力のシンボルでもある。国外で暮らす中国系住民にとって竜は、団結を支える存在であり、同時に父祖の地との心の結びつきを維持するために、大きな役割りを果たしている。(構成 / 如月隼人)

関連記事
羽生結弦さんのファンが抱える「幸せな悩み」―中国コラム
Record China
2023/2/20
台湾ドリンクブランド、日本進出で逆に「ひらがな→漢字」に=ネット民爆笑―台湾メディア
Record China
2023/2/20
シャンシャンとの別れ惜しむ日本の人々、「中国に会いに行く」という人も―中国メディア
Record China
2023/2/20
日本のZ世代が最も行きたい海外旅行地は?結果に韓国ネット「なぜ?」「韓国が勝つなんて!」
Record Korea
2023/2/20
日本でまた迷惑行為、ラーメン店で割り箸なめる男=中国SNSでトレンド入り
Record China
2023/2/20
10年後にサムスンが滅びる?韓国の半導体・ディスプレイ業界が焦る理由は
Record Korea
2023/2/20